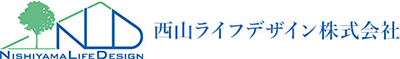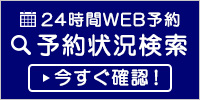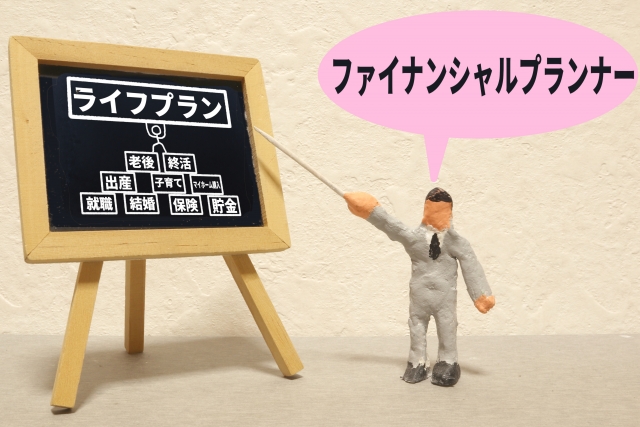祇園祭とともに過ごす夏 ― 神道の心と伝統の深み

今回は仕事とは関係ない話を。
7月17日に祇園祭の山鉾巡行に参加、菊水鉾の曳き方としてご奉仕してきました。
京都の夏を彩る祇園祭
京都では、毎年7月になると1か月にわたって祇園祭が行われます。
日本三大祭のひとつとして知られるこの祭りは、平安時代から続く長い歴史を持ち、神事と町衆の力が融合した、まさに「生きた文化遺産」ともいえる存在です。
私が祇園祭にご縁をいただいたのは十数年前のこと。
それ以来、毎年、前祭(さきまつり・7月17日)の山鉾巡行では菊水鉾(きくすいほこ)の曳き方として。
また神幸祭の神輿渡御では錦神輿会の一員として西御座神輿の担ぎ手を務めてきました。
7〜8年前からは、菊水鉾の曳き方の先頭を務めさせていただいています。
しかし今年は、4月に肩を骨折した影響もあり、先頭ではなく二番手に立ち、神輿の奉仕は辞退しました。
今年の山鉾巡行当日は大雨に見舞われるあいにくの天候でしたが、例年のような猛暑に苦しめられることもなく、無事にお勤めを果たすことができました。
毎年参加していても、祇園祭には改めて「奥の深さ」を感じさせられます。
山鉾巡行は神輿渡御の「お祓い」
実は、山鉾巡行は神輿渡御の「お祓い」にあたる行事であることは、あまり知られていないかもしれません。
神輿は「神様の乗り物」であり、その神様が町にお下りになる前に、山鉾が町を巡って厄を払うという重要な役割を果たしています。
山鉾は祭りの数日前から職人の手で丹念に組み立てられますが、巡行が終わるとすぐに解体されます。
これは、山鉾が町の厄を集め、それを封じ込める存在とされているためで、解体することによって厄が外へ逃げず、そのまま「消える」と信じられているからです。
動く美術館 ― 山鉾の懸装品に見る多様性
その山鉾ですが、「動く美術館」とも呼ばれるほど、豪華絢爛な懸装品(けそうひん)で装飾されています。
中にはペルシャ絨毯やベルギー製のタペストリーなど、海外のものが使われており、その絵柄にはキリスト教やギリシャ神話に由来するものも少なくありません。
祇園祭は「日本の祭り」でありながら、実に多様な文化を受け入れてきたことが伺えます。
この「多様性の受容」は、日本文化に根付いた神道の考え方に通じているように思います。
神道には「八百万(やおよろず)の神」という考えがあります。
自然、物、出来事、そして人の心にも神が宿るという思想です。
現在では日本神話に親しむ人は少なくなったかもしれませんが、「すべてに神が宿る」というこの感覚は、日本人の価値観の根幹にいまも息づいているように感じます。
神様が見ているという心の規範
私たちは子どもの頃、「誰も見ていなくても、神様が見ているよ」と言われたことがあるのではないでしょうか。
これは「悪いことをすれば罰が当たる」という戒めであり、「良いことをすれば神様が見ていてくれる」という希望でもあります。
日本には、目に見えないものに敬意を払い、他人のために積んだ徳を神様が必ず見てくれているという信仰が、生活の根にあります。
分断の時代にこそ、神道的な価値観を
いま、世界中で「分断」が問題となっています。
宗教、人種、思想の違いが衝突を生み、共に生きることが難しくなっている時代です。
そんな今だからこそ、すべてを受け入れ、調和を大切にする神道的な世界観が、ひとつのヒントになるのではないかと感じています。
祇園祭に毎年関わる中で、私はそのような神道の精神に触れ続けている気がします。
日本に古くから伝わるこのような奥深い伝統行事に関わることができていることを、私は心から誇りに思っています。